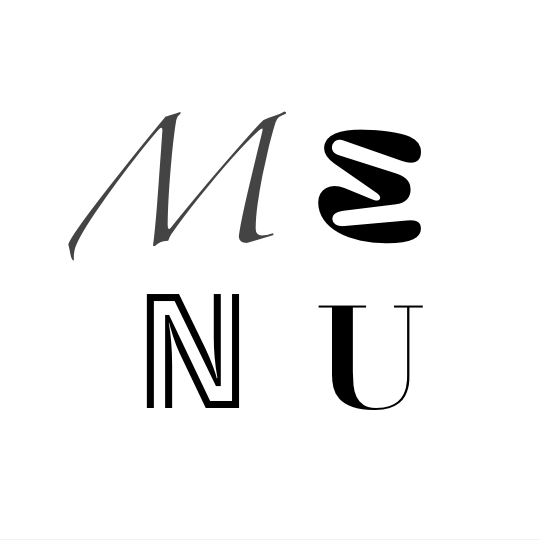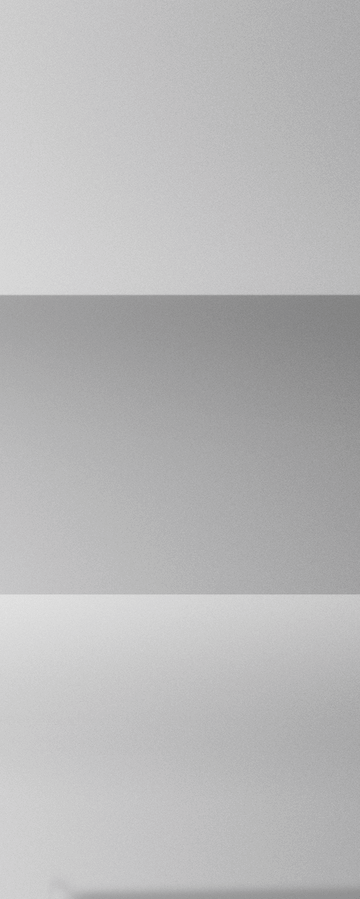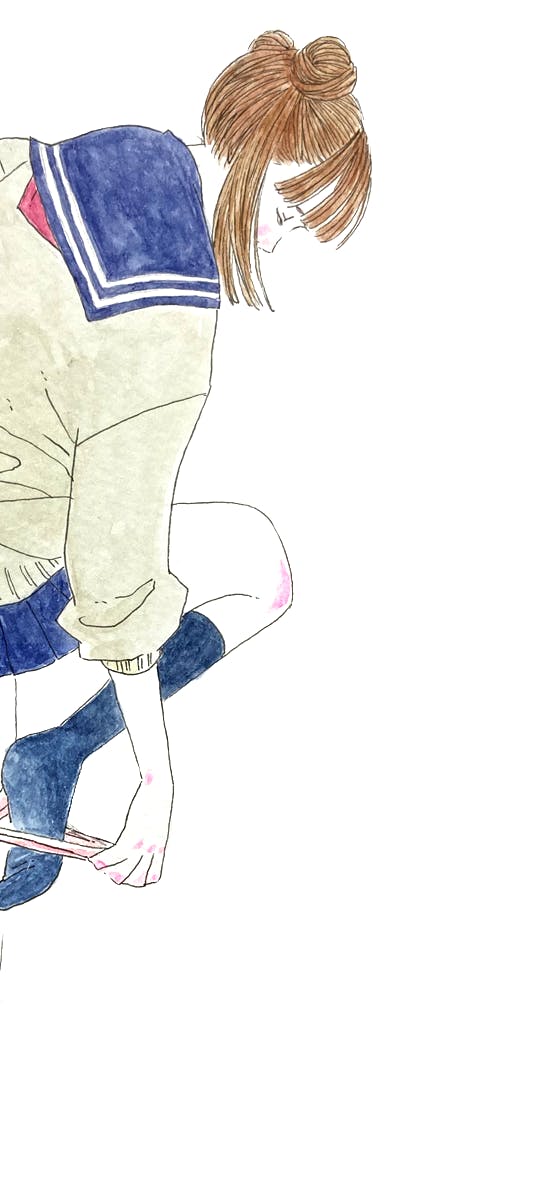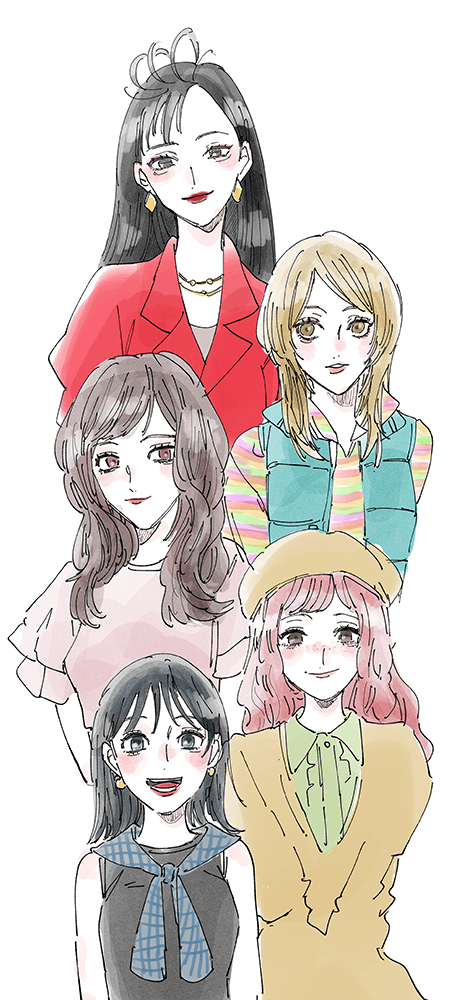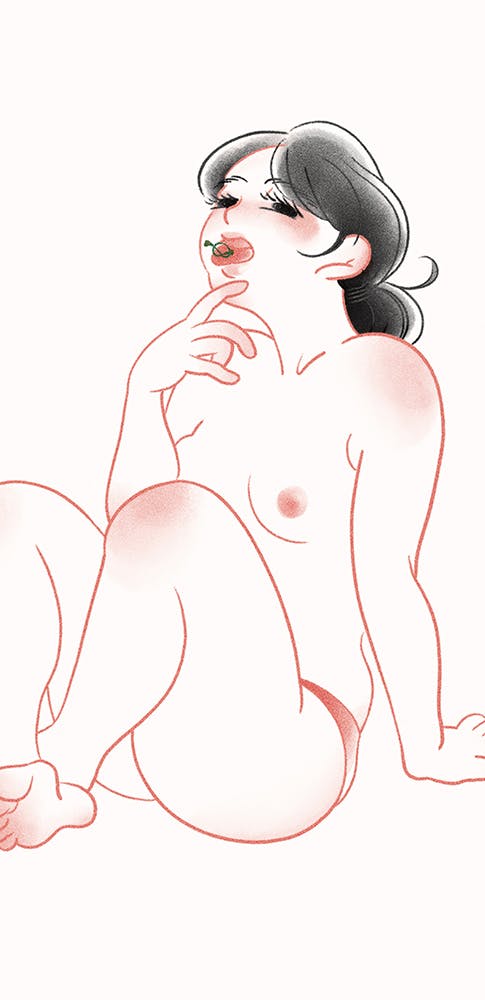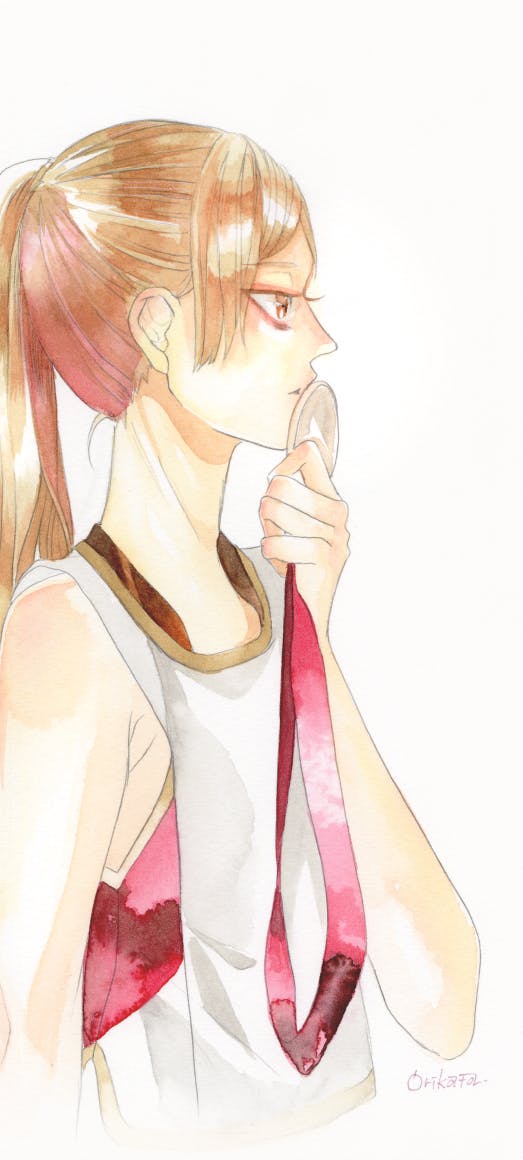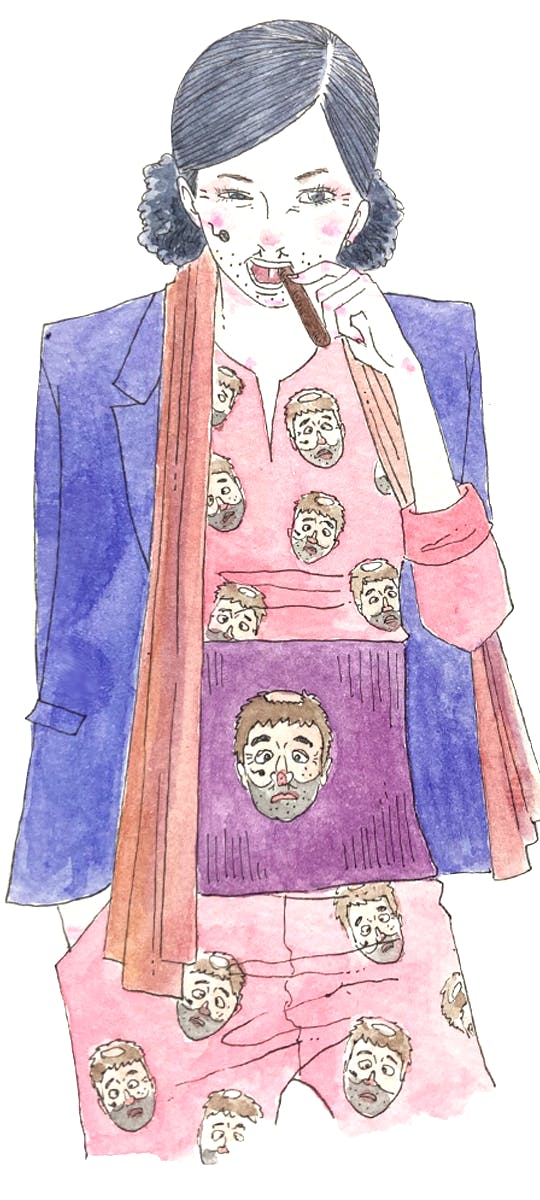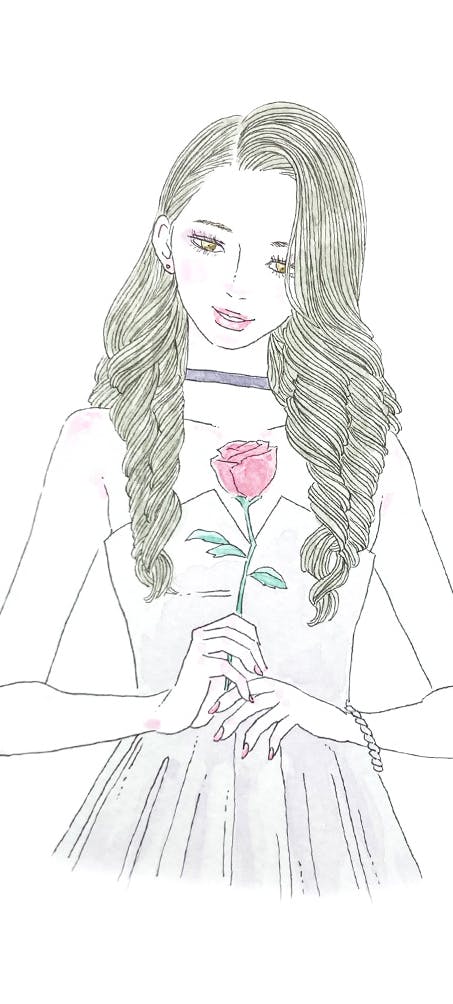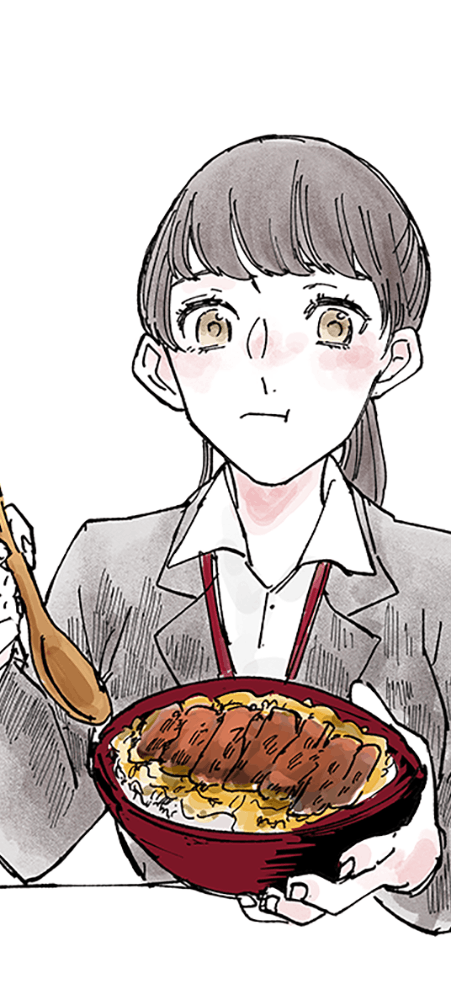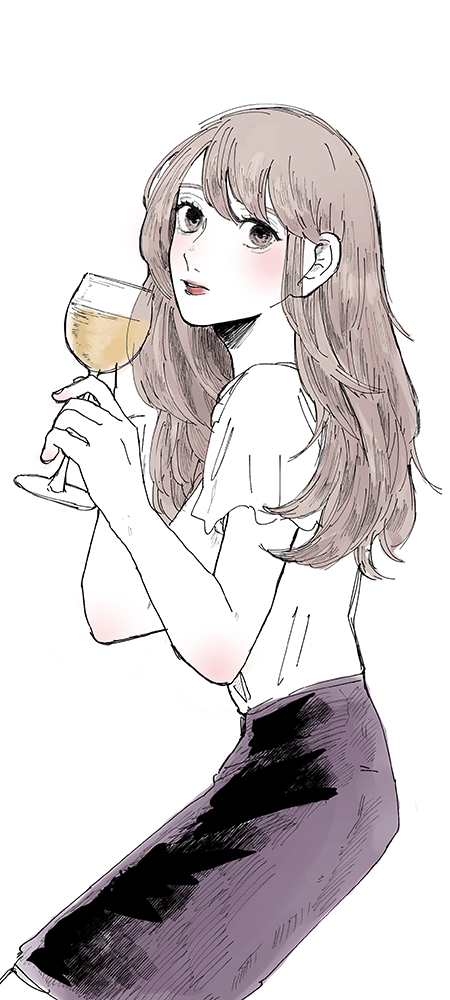あまり表に出してはいないが、私コミンズ・リオ、実は5歳から18歳までピアノを習っていた。そもそもなぜ始めたのかは今も覚えておらず、途中幾度となく辞めようと思いながらも、辞めたいと母親に相談しようと思うたび、うちの母親特有の逆張り攻撃「辞めたいならいつでも辞めてもいいんだよ〜(ドヤ顔)」戦法に見事にひっかかり、「今辞めてしまったら今まで練習してきた時間がもったいないし、何よりおかんのドヤ顔を今後さらに見続けなきゃいけない」という、わかりやすいサンクコストと謎のプライドに挟まれながら13年間も鍵盤に向かっていた。
ピアノを習っていた先生は、中学生半ばまでは日本人の女性だった。ポートランドに転勤で来ていた旦那さんについてきたいわゆる駐在妻で、地下にゲームルームがある大きな家に毎週習いに行ったのを覚えている。その先生が日本に帰国することになった時、新しい先生を紹介してくれた。その新しい先生は、「先生の先生」なのだと言われた。当時、とても不思議に思っていたのを覚えている。こんなにピアノが上手な先生にも先生がいるのか?中学生の自分みたく、大人の先生も誰かに習いにいくのか??そうだとしたら、それは一体どんな人間なのだ???
その新しい先生は「ボブちゃん」だった。そして後々理解することになるのだが、ボブちゃんは、今までの「ピアノのレッスン」とは全く違う体験を与える先生だった。ボブちゃんは、ポートランドの郊外の一つ、レイク・オスウィーゴという地域の、さらに僻地に住んでいた。小さな坂道を登り、ボブちゃん邸の前にたどり着くと、そこには何年も手入れがされてない鬱蒼とした木々が生い茂っている。茂みの中を無理やり車を通すと、少し奥のほうに一つの小さな家が現れる。こじんまりとした平家だ。メンテナンスが行き届いてない玄関扉のドアベルを鳴らすと、優しい笑顔でボブちゃんが出迎えてくれる。中に入ると、目に入るのは二つのものだけ:30インチぐらいの古いアナログテレビとスタインウェイのコンサートグランド。今まで習っていた日本人の先生の、大きくて白い邸宅…いたるところに綺麗な花が飾られ、地下のゲームルームにはビリヤード台があり、ピアノ以外の楽しい生活が垣間見える家とはまるで正反対の空間。薄暗く狭いリビングの中には、舞台装置にしか見えないテレビと、存在する場所を間違えたのではと思ってしまう、定価だと2000万円はする最高峰のピアノ。
ボブちゃんは天才に近いピアニストだった…らしい。「らしい」理由は、ボブちゃんのもとで習い始めてから入ってくる様々な情報の信憑性を確かめようがなかったからだ。世界トップレベルの名門音楽大学、ジュリアード音楽院を首席で卒業。コンサートピアニスト時代はオレゴンシンフォニーとのツアーを敢行*1。ボブちゃん自身のピアニストしての系譜は、ジュリアード時代の師匠を遡っていくと、数代でかのフランツ・リストにすら届くと言う。ボブちゃん自身ほとんど生徒の前で演奏をすることはなかったが、たまに特別な時に披露をしてくれた時(それこそリストの「ハンガリアン・ラプソディー」だったのを鮮明に覚えている)、背筋に稲妻が走った気がした。あまりにも圧倒的な演奏だった…あの瞬間、なぜ前の先生がボブちゃんに習っていたかがわかった気がした。これが「ピアノの先生」が学びにくる「ピアノの先生」か…。「先生」一つとってもレベルが全く違うのだ。
なぜそんなにすごいピアニストが、こんな僻地で、僕みたいな生徒を教えているのか。それはまだ幼かった自分でさえ常に脳内を巡る謎だった。引退後のコンサートピアニストがやりそうな、「世界を震撼させる次世代のピアニストの育成」からは程遠い、ピアノ・レッスンの継続の理由が「母親の想定通りに生きたくない」という不真面目な生徒(一例)を優しく見守る日々。その答えは、結局、「変人」だから、になるのだろう。ボブちゃんは、社会の「普通」からは完全に逸脱していた。まるで仙人のように家に籠り、ピアノを弾くか、本人曰く気分転換に映画を見るか(そのためのテレビらしい)。生徒と生徒の親以外の人間と関わっているのを見たことなかった。このような現状に至った理由は、コンサートピアニスト時代に燃え尽き、もう人前で演奏することに疲れてしまったから、らしい。それどころか、コンサートピアニストであり続けるための、「自分自身」を売る商売、「公」にい続けないといけない状態自体に疲れ、人間そのものとの関わりを最低限に抑えている生活を選んだ、という話だ。結局、これらも全部生徒の親たちの噂でしかなかったが。
===
自分の話に戻るが、三十路を超え、自分の中の「性格や価値観の濃度」に対する考えが変わっていくのを感じた。なぜ変わっていくのを感じたのかというと、自分自身が変わっていったからだ。元々社交的ではない性格の自分が、一時期を経て、本当に人とあんまり会わなくなった。もちろん仕事上は人と会うのだが、プライベートでは皆無。いくつかの新プロジェクトのスタートが諸々ゴールデンウィーク明けにリスケされた時など、仕事の予定がなくなったGW前の一週間は、あまりに人に会ってなく、レストランの店員に話しかけようとしても喉が働かず声が出なかったほどだ。音が出ない口をまるで金魚かのようにパクパクさせながら、初めて考えることに至った…どうしてこうなったのかと?
おそらく自分の中ではずっと(そしてもしかすると読者の中にも多くもそうかもしれないが)、極端な価値観や性格、いわゆる社会の中である個体を「変人」とさせている要素は、基本的には全て先天的なものが原因だと思っていた。例えば、電車のなかで大きな声でブツブツと独り言を呟いている男性は、生まれた瞬間から「そういった」障がいの持ち主なのだ、というように。もしくは、先天的ではなくても、明確なある瞬間やきっかけがあって、「そう」なってしまったのだと。元々は元気で活発だった女性が、最愛の一人息子が戦死したと報告を受けた日から、家から出ず人に会わなくなった、と言う例だ。なので、おそらく中学生の頃から、僕はボブちゃんも「そう」だったのだと思っていた。家に籠りピアノばっかり引いていた少年が、ジュリアードを出てコンサートピアニストになり、無理矢理自分の性格に合わないツアーやレコーディングなどを行い、疲弊し燃え尽きてしまい、元々の性格である「孤立」に戻ったーーそれが僕が勝手に思い描いたストーリーだったのだ。
しかし今は思う…本当にそうなのだろうか。だって自分をみてみよう。高校生の頃の自分が思い描いた30の時の自分は、今と全く違うものだ。あの時想像していた「大人」の自分は、常日頃からたくさんの人に囲まれているものだった。友達や仕事の関係者、たくさんの綺麗な女性と日々会い、社交的で華やかで生産性に溢れた日常を過ごしているイメージを持っていた。高校で開かれるダンスパーティを、「プロムとかで盛り上がってる奴らは全員ダサいし」と言い参加せず、卒業アルバムを「どうせこの先見ることなんて一度もないし」と言い注文せず母親を悲しませた*2、根暗で穿った中二病のコミンズ・リオ青年は、高校卒業と同時にオレゴン州に置いていかれるはずだった。しかし、今、むしろ逆の事態が起きている。あの頃の自分、言うなれば自分が生まれ持った「先天的」な性格の部分は、歳をとればとるほど濃くなっていってる。「根暗で穿った中二病」の高校生の自分は、それでも毎日友達に会ってはいたのだ。大学時代や20代前半は、今振り返ってみると(当社比になってしまうが)、かなり社交的な生活を送っていたのだ。
そこでボブちゃんのことを考える。もしかしたら…もしかしたらボブちゃんも昔は社交的だったのかもしれない。人前で演奏するのが好きでピアニストになり、コンサートが終わったあとの打ち上げにも楽しく参加し、自分のキャリアを後押ししてくれる人たちとの交流も有意義に行っていたのかもしれない。ただ、元から自分の中にあった「孤立」という名の小さな種が、一年また一年と時間が経つにつれ、少しずつ大きくなっていったのかもしれない。そして、その種が一つの立派な木となったタイミングに初めて、僕はボブちゃんと出会ったのかもしれない。
突然その日がやってくるのだろうか。いや、おそらく我々はちょっとずつ狂っていくんだ。自分がどうなるかは自分次第。ボブちゃんにいつかまた会うかはわからない。
高校三年生の時、人生で初めて作曲した曲をボブちゃんに見てもらった。ピアノ、フルート、クラリネット、チェロ、パーカッション様の輪舞曲だった。楽譜を渡した瞬間、ボブちゃんはピアノパートを弾き始めた。上記にもあるように、生徒の前でピアノを弾くことは珍しかったので、躊躇いなく突然弾き始めたことに僕はびっくりした。アインシュタインを彷彿させる乱れた銀髪に、クリスマス色の毛糸のセーター。ボブちゃんは意気揚々と楽しくその曲を弾き終わり、満面の笑顔で僕に言った「リオ、これは素晴らしいね曲だね!本当に楽しく演奏できたよ!」
僕はその瞬間を一生忘れない。
*注記*
*1: オレゴンシンフォニーといえば、漫画「のだめカンタービレ」のおかげで日本人にも知れ渡った名指揮者、ジェームズ・デプリースト氏とボブちゃんが共演したのかどうかはわからない。しかし、めっちゃ知りたい。
*2: 結局買ったのだが、読者のみな様はすでに予想しているであろう、いまだに一度も開いたことがない笑 むしろどこにあるのかもわからない…。